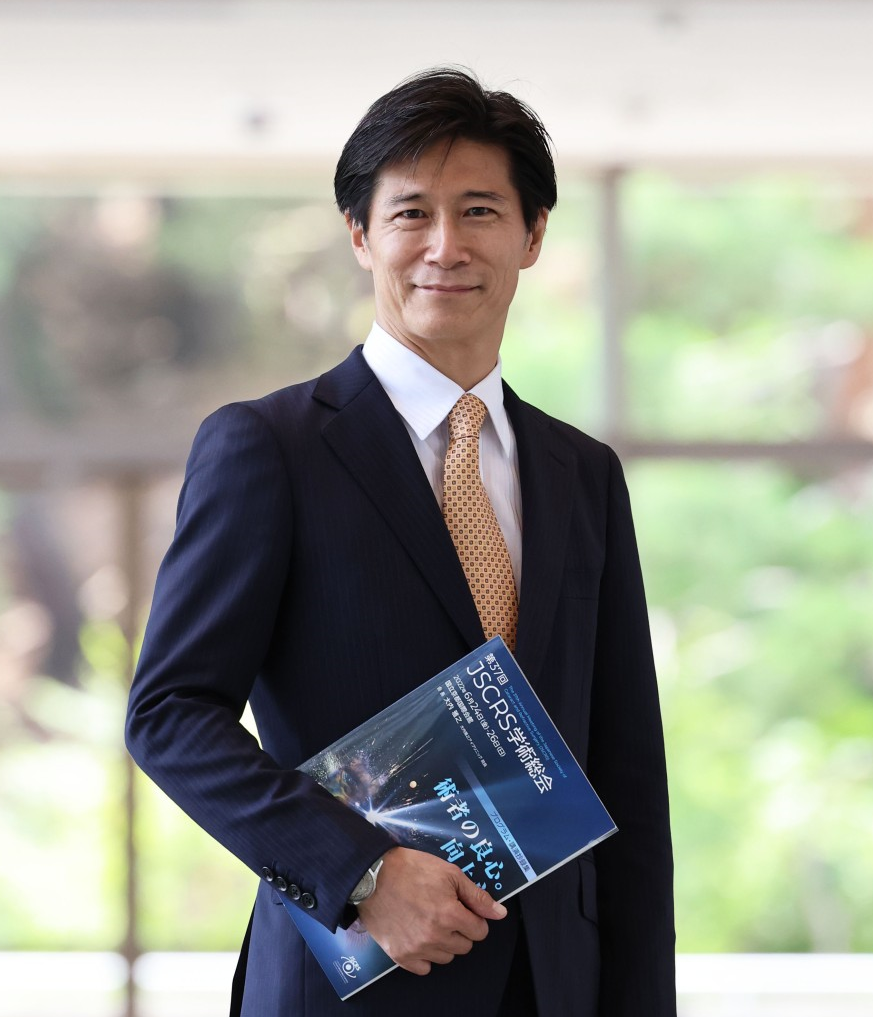糖尿病は、白内障を引き起こすリスクを大幅に高める原因の一つです。高血糖状態が目の水晶体にどのような影響を与えるのかを正しく理解し、適切な予防策を講じることで、大切な視力を守ることができます。
この記事では、糖尿病性白内障の原因や進行メカニズム、効果的な予防方法について詳しく解説します。健康的な生活習慣の重要性や血糖コントロールのポイントを再確認しながら、目の健康を守るための具体的なアドバイスをお届けします。
目次
糖尿病性白内障の特徴とは
糖尿病性白内障は、糖尿病を抱える方に特有の白内障です。一般的な白内障と比べて進行が早く、症状の現れ方にも違いがあります。
ここでは、その特徴や進行について詳しく見ていきましょう。
若年性と高齢者における発症パターン
糖尿病性白内障は、若年層の糖尿病患者にも発症することがあります。特に1型糖尿病の方は、血糖値の管理が難しい状態が続くことで、比較的若い年齢で発症するケースが報告されています。
一方で、高齢者の場合は、加齢による白内障に糖尿病性白内障が重なることがあります。この場合、白内障の進行がさらに早まる傾向にあります。
特に糖尿病歴が長い方は、そのリスクが高くなるとされています。
進行速度と症状の現れ方
糖尿病性白内障は、一般的な白内障と比べて進行が速いのが特徴です。
高血糖が水晶体に影響を及ぼし、短期間で視界がぼやけたり、霧がかかったように見えたりする症状が現れます。
進行すると、強い光を感じにくくなったり、暗い場所での視力低下が目立つようになります。
また、視界全体が黄色味を帯び、色のコントラストが失われることもあります。
このような症状が、高齢者以外にも起こり、また短期間で進むこともあるため、日常生活への影響が大きくなるのです。
糖尿病網膜症との違い
糖尿病網膜症は、糖尿病によって眼の奥=網膜の血管が傷み、出血や浮腫などで視力に影響を及ぼす病気です。高血糖が続くことで網膜の毛細血管がさらなる障害を受け、大きな出血や網膜剥離を引き起こすこともあります。
一方、糖尿病性白内障は眼の中のレンズ=水晶体が濁る病気で、網膜症とは発症の仕組みや治療法が異なります。
「まだ見えるから大丈夫」と油断せず、糖尿病が疑われる方は早めに眼科での定期検診を受けましょう。
糖尿病が白内障を引き起こす原因
糖尿病性白内障は、血糖値が慢性的に高い状態が続くことで発症します。その主なメカニズムを以下にまとめます。
血糖値の上昇とソルビトールの蓄積
血糖値が高いと、体内で余分な糖が「ソルビトール」という物質に変化します。このソルビトールが水晶体内に蓄積することで、水分バランスが崩れ、組織が膨張し透明性が失われます。
また、高血糖が水晶体のタンパク質を変性させるため、光が乱反射して視界がぼやける原因にもなります。
糖化による影響
糖尿病では、体内で「糖化」と呼ばれる反応が進行します。これは余分な糖がタンパク質に結びつき、組織の弾力性や透明性を低下させる現象です。水晶体でも糖化が進むと光の透過が妨げられ、視界がかすむ原因となります。このような変化は、血糖コントロールの状態に大きく影響されます。
糖尿病性白内障の具体的な6つの症状
白内障は、目の中にある水晶体が濁ることで発症し、視力にさまざまな影響を与える病気です。痛みはなく、初期段階では症状が軽いため気づきにくいことが多いですが、進行すると日常生活に支障をきたすこともあります。
ここでは、白内障の具体的な症状についてわかりやすくご説明します。
視界がかすむ・ぼやける
白内障の初期症状としてよく見られるのが、視界がかすんだり、ぼやけたりすることです。水晶体が徐々に濁ることで光がうまく通らなくなり、視界が白っぽく曇ったように感じられます。たとえるなら、曇ったガラス越しに物を見るような感覚です。
初期段階では、軽い違和感だけで済むことが多いですが、進行すると本や新聞の文字が読みづらくなったり、人の顔がはっきり見えなくなったりすることがあります。
光がまぶしく感じる(羞明)
白内障が進行すると、光に対して過敏になり、まぶしさを強く感じるようになります。この症状は「羞明(しゅうめい)」と呼ばれ、太陽光や車のヘッドライト、蛍光灯の光が特にまぶしく感じられるのが特徴です。夜間の運転中に、対向車のライトがまぶしすぎて目を開けていられなくなることもあります。
また、光が散乱しやすくなるため、光源の周りに輪のような光が見えることもあります。このような症状がある場合は、できるだけ夜間の運転を避け、早めに眼科を受診することをおすすめします。
視力が低下する
白内障が進行すると、徐々に視力が低下していきます。眼鏡やコンタクトレンズを使っても視力が改善しない場合は、白内障の可能性が高いです。
人間は両眼で物を見るため、片方の目の視力が低下してももう一方がカバーしてしまい、生活に大きな影響が出ないこともあります。しかし、そのまま放置すると症状が悪化し、手術の難度が上がる場合も。少しでも違和感があれば、早めに眼科を受診しましょう。
モノが二重に見える(複視)
白内障が進行すると、物が二重に見えることがあります。これは水晶体の濁りが不均一に広がることで、光の屈折が乱れるためです。片目を閉じても物が二重に見える場合は、白内障が原因の可能性が高く、特に、夜間のお月様が2重3重に見えると言う訴えは典型です。症状が進行するとさらに悪化するため、早めの診察を受けることが大切です。
色の見え方が変わる
白内障が進行すると、色の見え方にも変化が現れます。全体的に黄色っぽく見えたり、暗く感じたりすることが特徴です。これは水晶体が濁ることで一部の波長の光が透過しにくくなるからです。
白いものが黄ばんで見えたり、青や緑といった寒色系の色が識別しにくくなることもあります。信号や標識などの色の区別が難しくなるため、運転には注意が必要です。
視力の変動が激しくなる
白内障のタイプによっては、進行すると、視力が安定しなくなることがあります。たとえば、急に遠くが見えづらくなり、逆に近くが見えやすくなったりする症状です。これは水晶体の濁り方によって光の屈折が変わる(近視化)ために起こる現象です。
眼鏡やコンタクトレンズの度数を調整しても視力が安定しない、あるいは短期間に眼鏡・コンタクトの度数が上がるような場合は、白内障の疑いがあるので、早めに眼科を受診しましょう。
糖尿病性白内障のおもな2つの治療法
白内障の治療法は、病気の進行具合によって異なります。ここでは、主な治療法について詳しくご紹介します。
点眼薬による治療
初期段階では、点眼薬を用いて白内障の進行を抑えることもあります。ただし、完治や進行を完全に止めるような効果はありません。医師が処方する主な点眼薬には、以下の2種類がありますが、これらの効果には、懐疑的な意見も多く、積極的な処方は行わない医師も少なくありません。
グルタチオン製剤
水晶体に含まれるグルタチオンを補充し、白内障の進行を抑えます。
ピレノキシン製剤
水晶体の透明性を維持する効果があります。
市販の目薬もありますが、医療用ほどの効果は期待できません。定期的に眼科を受診し、適切な治療を受けることが大切です。
手術による治療
白内障が進行し、日常生活に支障をきたす場合は手術が必要です。手術では、濁った水晶体を取り除き、人工の水晶体(眼内レンズ)を挿入します。局所麻酔で行われ、日帰りで受けられる場合が多いです。
糖尿病がある場合は、手術前に血糖値のコントロールが重要です。高血糖状態で手術を行うと、術後感染のリスクが高まり、また糖尿病性網膜症の状態によってはこれが進行するリスクがあるため、医師と十分に相談してタイミングを決めましょう。
糖尿病性白内障を悪化させない方法
糖尿病性白内障は、適切な生活習慣を心がけることで予防や進行抑制が可能です。以下のポイントを参考にしてください。
血糖コントロールを徹底する
血糖値を適切に管理することが最も重要です。食事療法や運動を取り入れ、医師の指導のもとで治療計画を立てましょう。食物繊維が豊富な食品を優先して摂ることで、血糖値の急激な変動を抑えることができます。
紫外線から目を守る
紫外線は水晶体の酸化を進める原因の一つです。外出時は紫外線カット効果のあるサングラスや帽子を活用し、目を保護しましょう。
栄養バランスを考慮した食事を心がける
目の健康を保つためには、栄養バランスの取れた食事が欠かせません。
ビタミンCやビタミンE、ルテインなどの栄養素を含む食品を積極的に摂取することで、目の健康を保つことができます。
具体的には、柑橘類や緑黄色野菜、魚介類などがこれらの栄養素を多く含んでいます。
毎日の食事にこれらの食品を取り入れることで、目の健康をサポートすることが可能です。
定期的に眼科検診を受ける
糖尿病性白内障は早期発見が鍵です。定期的な眼科検診を受けることで、早期の対策が可能です。
眼科検診では、視力の測定だけでなく、水晶体の透明度や網膜の状態がある程度以上悪化すれば、それも確認できます。
異常を早期に発見することで、必要な治療を迅速に行うことができます。
健康的な生活習慣を維持する
規則正しい生活を心がけ、ストレス管理や禁煙にも努めましょう。また、適度な運動を習慣化することで、全身の健康を保つことができます。
糖尿病性白内障を防ぐためには、日々の小さな心がけが大切です。早めの対策で健康な目を守りましょう。
おわりに
糖尿病性白内障を予防するには、血糖値の管理、紫外線対策、バランスの取れた食事、定期的な眼科検診が欠かせません。
さらに、過度な飲酒や、血行を悪くさせる喫煙を控え、健康的な生活習慣を維持することが重要です。
これらを日常生活に取り入れることで、白内障だけでなく他の合併症のリスクも軽減できます。
眼に違和感があったら、すぐにかかりつけの医師に診てもらいましょう。
医師の判断のもと、適切なタイミングで手術をしてもらってください。
たいせつな視力を守るために、今日からできることを始めましょう。